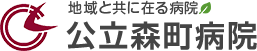【令和5年度】同報無線による森町病院からのお知らせ
令和6年3月のお知らせ
放送日:令和6年3月15日
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、新型コロナウイルス感染症に対する医療提供体制の変更についてと、当院の来院前事前AI問診の状況についてお話します。
新型コロナ感染症の医療提供体制については、国の方針として、本年4月からインフルエンザなどと同様の通常の保険診療に移行することが決まっています。昨年10月からは、それまで全額公費負担であった医療費について一部自己負担となっていましたが、自己負担の上限額が定められており、その上限額を超えた差額は公費負担となっていました。本年4月からはその公費負担もなくなります。したがって、抗ウィルス薬など高額の薬剤を使用する場合は、それなりに自己負担も発生しますので、処方を希望する場合は、そのことを踏まえて医師とよく相談してください。
新型コロナウイルス感染症の発生状況は、1月末から2月初旬をピークとして、その後減少傾向にあります。インフルエンザも同様です。しかしながら、当院では、今月に入ってからも連日多くの患者さんが発熱外来を受診しています。一時期に比べ減少傾向ではありますが、一定程度の感染者は発生しています。医療費の負担を減らすためにも、今後も引き続き感染対策には注意してください。
先月の同報無線で、来院前事前AI問診についてお話しました。患者さんの待ち時間や医師の負担を減らすために、事前にAI問診の入力のご協力をお願いしたところ、放送の当日から発熱外来の約8割の方がAI問診を入力していただいています。予想を上回る結果に対して森町住民の意識の高さに感心させられました。また発熱外来を担当する医師たちからも好評価を得ており院長として心から感謝申し上げます。現在も発熱外来の多くの方が、事前AI問診の入力を行っていただいています。
当院でAI問診を導入してしばらくの間は、来院してから職員が補助してAI問診を行っていただいていましたが、入力に手間がかかりかえって診察までの時間が長くなってしまう場合もありました。今後はできるだけ、来院前に事前AI問診を入力していただくことで、よりこのシステムの効果が発揮されます。ご高齢の方は、入力するためにご家族に手伝っていただく必要があるかもしれませんが、それによってご家族も患者さんの状況を理解するきっかけにもなります。これからの超高齢化時代において、患者さんの思いや価値観なども含め、ご家族でさまざまな情報を共有することは非常に重要となります。AI問診をきっかけとして、森町にデジタル技術活用の文化が根付くことを期待しています。今後とも地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、新型コロナウイルス感染症に対する医療提供体制の変更についてと、当院の来院前事前AI問診の状況についてお話します。
新型コロナ感染症の医療提供体制については、国の方針として、本年4月からインフルエンザなどと同様の通常の保険診療に移行することが決まっています。昨年10月からは、それまで全額公費負担であった医療費について一部自己負担となっていましたが、自己負担の上限額が定められており、その上限額を超えた差額は公費負担となっていました。本年4月からはその公費負担もなくなります。したがって、抗ウィルス薬など高額の薬剤を使用する場合は、それなりに自己負担も発生しますので、処方を希望する場合は、そのことを踏まえて医師とよく相談してください。
新型コロナウイルス感染症の発生状況は、1月末から2月初旬をピークとして、その後減少傾向にあります。インフルエンザも同様です。しかしながら、当院では、今月に入ってからも連日多くの患者さんが発熱外来を受診しています。一時期に比べ減少傾向ではありますが、一定程度の感染者は発生しています。医療費の負担を減らすためにも、今後も引き続き感染対策には注意してください。
先月の同報無線で、来院前事前AI問診についてお話しました。患者さんの待ち時間や医師の負担を減らすために、事前にAI問診の入力のご協力をお願いしたところ、放送の当日から発熱外来の約8割の方がAI問診を入力していただいています。予想を上回る結果に対して森町住民の意識の高さに感心させられました。また発熱外来を担当する医師たちからも好評価を得ており院長として心から感謝申し上げます。現在も発熱外来の多くの方が、事前AI問診の入力を行っていただいています。
当院でAI問診を導入してしばらくの間は、来院してから職員が補助してAI問診を行っていただいていましたが、入力に手間がかかりかえって診察までの時間が長くなってしまう場合もありました。今後はできるだけ、来院前に事前AI問診を入力していただくことで、よりこのシステムの効果が発揮されます。ご高齢の方は、入力するためにご家族に手伝っていただく必要があるかもしれませんが、それによってご家族も患者さんの状況を理解するきっかけにもなります。これからの超高齢化時代において、患者さんの思いや価値観なども含め、ご家族でさまざまな情報を共有することは非常に重要となります。AI問診をきっかけとして、森町にデジタル技術活用の文化が根付くことを期待しています。今後とも地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
令和6年2月のお知らせ
放送日:令和6年2月15日
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、当院のAI問診についてお話します。
12月の同報無線でもお話しましたが、当院では、来院前事前AI問診というシステムを取り入れています。これは、ご自身のスマートフォンやタブレット、パソコン等で、自宅などで来院前に問診ができる仕組みです。画面に表示される質問項目に答える形で、いつからどのような症状があるかなどを入力していただくと、AIが経過をわかりやすくまとめて文章化します。そのまま、電子カルテに取り込むことも可能なため、待ち時間や診察時間を短縮することができます。AI問診を用いた受診の流れは、まずは病院へ電話連絡していただき、外来の予約をします。その後、当院のホームページから来院時事前AI問診を開いて、「問診を始める」ボタンを押して開始し、画面に表示される質問に最後まで答えていただきます。問診が終了すると受付番号が表示されます。受診の際に必要になりますので、その控えを必ず取ってください。また、事前に電話による予約は必ず行ってください。問診の入力は、24時間いつでも可能です。ご自分の都合の良い時間に入力が可能です。詳しくは、森町病院のホームページでご確認いただくか、当院医事課までお問い合わせください。
現在、森町でも新型コロナ感染症が増え続けており、減少する兆しが見えません。インフルエンザも多く発生しています。当院では、院内感染を防ぐために、発熱患者さんは、病院のサービスヤードに設けたドライブスルー形式の発熱外来で診察を行っています。連日多くの方が発熱外来を受診され、医師は多くの業務の合間に診察を行うため、患者さんが増えれば増えるほど待ち時間も長くなってしまいます。患者さんは車の中で待機していただくことになりますが、事前AI問診を入力していただければ、時間を短縮することができ、必要な場合に直ちに検査に進むことが可能となります。患者さんにとっても待ち時間を短縮することができるメリットがあると同時に当院医師の負担を減らすことにもつながります。
いまや、インターネットは日々の生活に欠かすことのできないものとなっています。今後高齢者人口が増える中で働く世代の人口が減少することから、IT機器を用いた業務の効率化は、すべての分野で必須になってきます。日本では世界に比べてITの活用が遅れていると言われています。特に医療界のIT化は遅れています。森町は、近隣市町と比べても高齢化が進んだ町であり、森町こそがIT機器やAI技術を有効活用した町づくりをすべきであると考えています。ご高齢の方も、難しく考えず、若い人の力を借りるなどして、事前AI問診を使ってみてはいかがでしょうか。まずはやってみるという姿勢が必要だと思います。これからの医療を持続可能なものとするため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、当院のAI問診についてお話します。
12月の同報無線でもお話しましたが、当院では、来院前事前AI問診というシステムを取り入れています。これは、ご自身のスマートフォンやタブレット、パソコン等で、自宅などで来院前に問診ができる仕組みです。画面に表示される質問項目に答える形で、いつからどのような症状があるかなどを入力していただくと、AIが経過をわかりやすくまとめて文章化します。そのまま、電子カルテに取り込むことも可能なため、待ち時間や診察時間を短縮することができます。AI問診を用いた受診の流れは、まずは病院へ電話連絡していただき、外来の予約をします。その後、当院のホームページから来院時事前AI問診を開いて、「問診を始める」ボタンを押して開始し、画面に表示される質問に最後まで答えていただきます。問診が終了すると受付番号が表示されます。受診の際に必要になりますので、その控えを必ず取ってください。また、事前に電話による予約は必ず行ってください。問診の入力は、24時間いつでも可能です。ご自分の都合の良い時間に入力が可能です。詳しくは、森町病院のホームページでご確認いただくか、当院医事課までお問い合わせください。
現在、森町でも新型コロナ感染症が増え続けており、減少する兆しが見えません。インフルエンザも多く発生しています。当院では、院内感染を防ぐために、発熱患者さんは、病院のサービスヤードに設けたドライブスルー形式の発熱外来で診察を行っています。連日多くの方が発熱外来を受診され、医師は多くの業務の合間に診察を行うため、患者さんが増えれば増えるほど待ち時間も長くなってしまいます。患者さんは車の中で待機していただくことになりますが、事前AI問診を入力していただければ、時間を短縮することができ、必要な場合に直ちに検査に進むことが可能となります。患者さんにとっても待ち時間を短縮することができるメリットがあると同時に当院医師の負担を減らすことにもつながります。
いまや、インターネットは日々の生活に欠かすことのできないものとなっています。今後高齢者人口が増える中で働く世代の人口が減少することから、IT機器を用いた業務の効率化は、すべての分野で必須になってきます。日本では世界に比べてITの活用が遅れていると言われています。特に医療界のIT化は遅れています。森町は、近隣市町と比べても高齢化が進んだ町であり、森町こそがIT機器やAI技術を有効活用した町づくりをすべきであると考えています。ご高齢の方も、難しく考えず、若い人の力を借りるなどして、事前AI問診を使ってみてはいかがでしょうか。まずはやってみるという姿勢が必要だと思います。これからの医療を持続可能なものとするため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
令和6年1月のお知らせ
放送日:令和6年1月15日
担当者:院長 中村昌樹
新年あけましておめでとうございます。今年は、元日から能登半島地震という大災害に見舞われ、波乱の幕開けと言っていい年になりました。能登半島地震では多くの方がお亡くなりになり、未だに安否不明の方もいらっしゃいます。また、今の寒い季節、避難所で過ごすことを余儀なくされている方々も大変つらい思いをしていることと思います。被災者の方々には心からお見舞い申し上げたいと思います。
こんな時こそ、医療が最も重要な安全保障の仕組みであると感じます。同時に、医療は国を始めとした行政や多くの人々の支援なしには成り立たないとも思います。被災現場で救助に当たる人、道路の修復や物資の調達に携わる人、また全体を統括する人、様々な役割が機能して初めて医療も成り立ちます。被災地の医療機関の職員は、人々の命を支えるため日夜奮闘していることと思います。一方、被災現場の医療従事者もまた被災者です。そんな時に頼りになるのは外からの支援です。当院も人員不足ではありますが、災害支援ナースを派遣する予定です。今回のことで、改めて人と人、地域と地域がつながり、支えあうことの大切さに気づかされます。
医療の当事者とは、決して医療機関だけではありません。自ら健康を守ろうとする住民、生活を支える様々な職種や行政、また専門職を育てる教育機関の役割も重要です。それぞれがその役割を果たしてこそ医療は成り立ちます。当院は、そのような観点から地域のネットワークづくりに取り組んできました。多職種合同カンファレンスの開催や介護施設に定期的に往診し、今年度からは地域包括支援センターに、リハビリ職員を出向させています。地域住民との連携では、結成から13年たった森町病院友の会が病院と地域の架け橋の役割を果たしています。さらにこのような医療を支援する住民の会が、市町の垣根を超えたネットワークを構築しています。このことは、全国的にも稀なことです。近隣医療機関との機能分化と連携を進めてきたことも、コロナ禍を乗り越える上で効果を発揮しました。浜松医科大学との連携も重視しています。我々が立ち上げた家庭医養成プログラムも、浜松医大総合診療医プログラムに発展しています。昨年浜松医大に寄付講座として、森町地域包括ケア講座が設置されたことは、今後の医学教育においても重要な意味を持ちます。
これまでの医学教育は、大学を中心とした高度急性期病院が主体になってきました。しかしながら世界的な流れは、特殊な疾患のみが集まる大学病院ではなく、地域で頻度の高い多様な疾患に対応できる医師の育成を重視する方向に変化しています。日本でも同様に、地域の医療現場で学ぶことが求められ、当院もこれまで多くの学生や研修医を受け入れてきました。当院のような中小病院で学ぶことは、単に疾患に焦点を当てるだけではなく、生活者にとって必要な医療とは何かを学ぶことです。世界的に高齢化が進む中、病気の治療だけでは解決しない問題もますます増えてきます。そんな時代に必要とされる医療者には総合的視点が求められ、多職種や住民との関わりが重要になってきます。したがって医学教育においても、当院のような生活圏の医療を担う中小病院の役割が大きくなってきます。また地域で学んだ若者の中から、将来地域医療に携わりたいと思う医師が育つことも期待されます。日本の医療の未来を支えるためにも、ぜひとも地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
担当者:院長 中村昌樹
新年あけましておめでとうございます。今年は、元日から能登半島地震という大災害に見舞われ、波乱の幕開けと言っていい年になりました。能登半島地震では多くの方がお亡くなりになり、未だに安否不明の方もいらっしゃいます。また、今の寒い季節、避難所で過ごすことを余儀なくされている方々も大変つらい思いをしていることと思います。被災者の方々には心からお見舞い申し上げたいと思います。
こんな時こそ、医療が最も重要な安全保障の仕組みであると感じます。同時に、医療は国を始めとした行政や多くの人々の支援なしには成り立たないとも思います。被災現場で救助に当たる人、道路の修復や物資の調達に携わる人、また全体を統括する人、様々な役割が機能して初めて医療も成り立ちます。被災地の医療機関の職員は、人々の命を支えるため日夜奮闘していることと思います。一方、被災現場の医療従事者もまた被災者です。そんな時に頼りになるのは外からの支援です。当院も人員不足ではありますが、災害支援ナースを派遣する予定です。今回のことで、改めて人と人、地域と地域がつながり、支えあうことの大切さに気づかされます。
医療の当事者とは、決して医療機関だけではありません。自ら健康を守ろうとする住民、生活を支える様々な職種や行政、また専門職を育てる教育機関の役割も重要です。それぞれがその役割を果たしてこそ医療は成り立ちます。当院は、そのような観点から地域のネットワークづくりに取り組んできました。多職種合同カンファレンスの開催や介護施設に定期的に往診し、今年度からは地域包括支援センターに、リハビリ職員を出向させています。地域住民との連携では、結成から13年たった森町病院友の会が病院と地域の架け橋の役割を果たしています。さらにこのような医療を支援する住民の会が、市町の垣根を超えたネットワークを構築しています。このことは、全国的にも稀なことです。近隣医療機関との機能分化と連携を進めてきたことも、コロナ禍を乗り越える上で効果を発揮しました。浜松医科大学との連携も重視しています。我々が立ち上げた家庭医養成プログラムも、浜松医大総合診療医プログラムに発展しています。昨年浜松医大に寄付講座として、森町地域包括ケア講座が設置されたことは、今後の医学教育においても重要な意味を持ちます。
これまでの医学教育は、大学を中心とした高度急性期病院が主体になってきました。しかしながら世界的な流れは、特殊な疾患のみが集まる大学病院ではなく、地域で頻度の高い多様な疾患に対応できる医師の育成を重視する方向に変化しています。日本でも同様に、地域の医療現場で学ぶことが求められ、当院もこれまで多くの学生や研修医を受け入れてきました。当院のような中小病院で学ぶことは、単に疾患に焦点を当てるだけではなく、生活者にとって必要な医療とは何かを学ぶことです。世界的に高齢化が進む中、病気の治療だけでは解決しない問題もますます増えてきます。そんな時代に必要とされる医療者には総合的視点が求められ、多職種や住民との関わりが重要になってきます。したがって医学教育においても、当院のような生活圏の医療を担う中小病院の役割が大きくなってきます。また地域で学んだ若者の中から、将来地域医療に携わりたいと思う医師が育つことも期待されます。日本の医療の未来を支えるためにも、ぜひとも地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
令和5年12月のお知らせ
放送日:令和5年12月15日
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、当院のAI問診と人生会議についてお話します。
まずAI問診についてですが、当院は初診でかかる患者さんにタブレットなどのIT機器を使用したAI問診を行っています。これは、画面に表示される質問事項に答える形で、症状や経過、受診の目的などを入力すると、AIがその経過をまとめてわかりやすく文章化するものです。そのまま電子カルテに取り込むこともできるため、診療の補助として使えるばかりでなく、患者さんの待ち時間を短縮する効果も期待されます。ただし、質問項目が多く、すべて答えるのに少し時間がかかるという問題があります。そのため、病院に来てから入力するのではなく、受診前に自宅で、ご自分のパソコンやスマートフォンで入力することもできるようにしています。当院のホームページの、「外来を受診される方」というタブをクリックすると、左側の項目の一番上に来院時事前AI問診という項目があり、そこから問診の画面に入ることができます。受診を希望する方は、事前に病院に電話で受診予約をしてから事前AI問診を行っていただき、事前問診が難しい方は、病院に来てから職員の補助のもと、タブレットで入力してもらうことになります。質問にすべて答えるのに5分ほどかかりますが、途中で中止することも可能です。
次に人生会議についてですが、これはアドバンスケアプランニング(ACP)という言葉を、日本語で表現したものです。ご自分が人生において何を大切にしているか、どのような生き方をしたいかなど、高齢や病気などでご自分の意思をうまく表現できなくなる前に、ご家族や医療関係者などと話し合っておこうというものです。人生の最終段階をどこでどのように過ごしたいかなど、自分の思いを伝えておくことは大切です。当院の基本方針の3番目に、「保健・福祉との連携で、患者さまの価値観を支える医療を提供します」と掲げています。この方針に合致した医療を提供するために、人生会議は非常に大きな意味を持ってきます。
2025年には団塊の世代が後期高齢者となり、森町でも多くの方が人生の最終段階を迎えることになります。これまで当院が築いてきた多職種連携の仕組みや、在宅医療提供体制がさらに本領発揮する時代です。森町保健福祉センターのアンケート調査によると、最期は家で迎えたいが実現困難だと思っている方が多いという結果でした。当院と森町家庭医療クリニックの死亡診断書によると、令和4年度は亡くなられた方の47%が自宅で最期を迎えています。森町では在宅医療も実現可能な選択肢として提供できていることがわかります。今年、森町版こころのノートが作成されました。自分の思いを書き記すための一つの手段です。地域包括支援センターや当院でも配布しています。そのようなものをきっかけとして、ご家族と話し合うことも良いのではないでしょうか。人それぞれの豊かな人生を最期まで支えるために、地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、当院のAI問診と人生会議についてお話します。
まずAI問診についてですが、当院は初診でかかる患者さんにタブレットなどのIT機器を使用したAI問診を行っています。これは、画面に表示される質問事項に答える形で、症状や経過、受診の目的などを入力すると、AIがその経過をまとめてわかりやすく文章化するものです。そのまま電子カルテに取り込むこともできるため、診療の補助として使えるばかりでなく、患者さんの待ち時間を短縮する効果も期待されます。ただし、質問項目が多く、すべて答えるのに少し時間がかかるという問題があります。そのため、病院に来てから入力するのではなく、受診前に自宅で、ご自分のパソコンやスマートフォンで入力することもできるようにしています。当院のホームページの、「外来を受診される方」というタブをクリックすると、左側の項目の一番上に来院時事前AI問診という項目があり、そこから問診の画面に入ることができます。受診を希望する方は、事前に病院に電話で受診予約をしてから事前AI問診を行っていただき、事前問診が難しい方は、病院に来てから職員の補助のもと、タブレットで入力してもらうことになります。質問にすべて答えるのに5分ほどかかりますが、途中で中止することも可能です。
次に人生会議についてですが、これはアドバンスケアプランニング(ACP)という言葉を、日本語で表現したものです。ご自分が人生において何を大切にしているか、どのような生き方をしたいかなど、高齢や病気などでご自分の意思をうまく表現できなくなる前に、ご家族や医療関係者などと話し合っておこうというものです。人生の最終段階をどこでどのように過ごしたいかなど、自分の思いを伝えておくことは大切です。当院の基本方針の3番目に、「保健・福祉との連携で、患者さまの価値観を支える医療を提供します」と掲げています。この方針に合致した医療を提供するために、人生会議は非常に大きな意味を持ってきます。
2025年には団塊の世代が後期高齢者となり、森町でも多くの方が人生の最終段階を迎えることになります。これまで当院が築いてきた多職種連携の仕組みや、在宅医療提供体制がさらに本領発揮する時代です。森町保健福祉センターのアンケート調査によると、最期は家で迎えたいが実現困難だと思っている方が多いという結果でした。当院と森町家庭医療クリニックの死亡診断書によると、令和4年度は亡くなられた方の47%が自宅で最期を迎えています。森町では在宅医療も実現可能な選択肢として提供できていることがわかります。今年、森町版こころのノートが作成されました。自分の思いを書き記すための一つの手段です。地域包括支援センターや当院でも配布しています。そのようなものをきっかけとして、ご家族と話し合うことも良いのではないでしょうか。人それぞれの豊かな人生を最期まで支えるために、地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
令和5年11月のお知らせ
放送日:令和5年11月15日
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、糖尿病性腎症についてお話します。
静岡県が独自に公表している、健康寿命の指標であるお達者度では、森町は男女ともに県内市町の中でも常に上位に位置しています。しかしながら、森町は県の平均と比べて糖尿病と慢性腎臓病の有病率が高いことが指摘されています。慢性腎臓病の原因は様々ですが、腎透析が必要となる原因疾患で最も多いのが糖尿病です。そこで、森町では、糖尿病性腎症重症化予防プログラムを立ち上げ、様々な取り組みを行っています。当院と森町家庭医療クリニックも町と協力体制をとり、日頃の健康管理に携わっています。
高血糖は腎臓の細胞に直接的な影響を及ぼすことで腎臓の機能を損ないます。また高血糖による動脈硬化の進行も腎臓に悪影響を及ぼします。これにより、腎臓の基本的な機能である血液中の老廃物や水分の排泄が妨げられ、重症化すると生命を維持するために透析が必要となります。静岡県のホームページでも公開されていますが、市町ごとの標準化死亡比をみると、森町はやはり死因として慢性腎臓病が多くなっています。初期には症状がほとんどなく、自覚症状が出にくいため、検査を行わないと腎症が進んでいるかどうかはわかりません。糖尿性腎症の予防や管理には、まず糖尿病の適切なコントロールが不可欠です。適切な血糖管理を行うことで、糖尿病性腎症の進行を遅らせることができます。また血圧やコレステロールの管理も重要です。重症化すればするほど医療費が増大するだけでなく、何よりも患者さん自身の生活が制限されることになります。現在は糖尿病をコントロールする薬も進歩して腎臓病の進展を予防する効果が認められる薬も使えるようになりました。たとえ糖尿病という病名がついてもしっかりコントロールすれば天寿を全うすることも可能な時代になっています。健診などで高血糖を指摘された方は、ぜひ医療機関を受診してください。
今後も森町では後期高齢者人口が増加し、ますます慢性疾患を抱える人が増えてきます。当院と森町家庭医療クリニックは、生活圏で医療を提供するのが役割です。より重症化し専門的医療が必要になった場合は、高度急性期病院に紹介します。高度急性期病院では、それだけの人員と設備を備えているため、当然医療費も高くなります。医療費の観点だけでなく、患者さんの生活を守るためにも、身近な医療機関での、重症化させない医療が重要になります。医療は生活者にとって最も基本的な安全保障のシステムだと考えます。医療機関の役割に応じた適切なかかり方を選択することで、地域医療を持続可能なものとすることに、地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、糖尿病性腎症についてお話します。
静岡県が独自に公表している、健康寿命の指標であるお達者度では、森町は男女ともに県内市町の中でも常に上位に位置しています。しかしながら、森町は県の平均と比べて糖尿病と慢性腎臓病の有病率が高いことが指摘されています。慢性腎臓病の原因は様々ですが、腎透析が必要となる原因疾患で最も多いのが糖尿病です。そこで、森町では、糖尿病性腎症重症化予防プログラムを立ち上げ、様々な取り組みを行っています。当院と森町家庭医療クリニックも町と協力体制をとり、日頃の健康管理に携わっています。
高血糖は腎臓の細胞に直接的な影響を及ぼすことで腎臓の機能を損ないます。また高血糖による動脈硬化の進行も腎臓に悪影響を及ぼします。これにより、腎臓の基本的な機能である血液中の老廃物や水分の排泄が妨げられ、重症化すると生命を維持するために透析が必要となります。静岡県のホームページでも公開されていますが、市町ごとの標準化死亡比をみると、森町はやはり死因として慢性腎臓病が多くなっています。初期には症状がほとんどなく、自覚症状が出にくいため、検査を行わないと腎症が進んでいるかどうかはわかりません。糖尿性腎症の予防や管理には、まず糖尿病の適切なコントロールが不可欠です。適切な血糖管理を行うことで、糖尿病性腎症の進行を遅らせることができます。また血圧やコレステロールの管理も重要です。重症化すればするほど医療費が増大するだけでなく、何よりも患者さん自身の生活が制限されることになります。現在は糖尿病をコントロールする薬も進歩して腎臓病の進展を予防する効果が認められる薬も使えるようになりました。たとえ糖尿病という病名がついてもしっかりコントロールすれば天寿を全うすることも可能な時代になっています。健診などで高血糖を指摘された方は、ぜひ医療機関を受診してください。
今後も森町では後期高齢者人口が増加し、ますます慢性疾患を抱える人が増えてきます。当院と森町家庭医療クリニックは、生活圏で医療を提供するのが役割です。より重症化し専門的医療が必要になった場合は、高度急性期病院に紹介します。高度急性期病院では、それだけの人員と設備を備えているため、当然医療費も高くなります。医療費の観点だけでなく、患者さんの生活を守るためにも、身近な医療機関での、重症化させない医療が重要になります。医療は生活者にとって最も基本的な安全保障のシステムだと考えます。医療機関の役割に応じた適切なかかり方を選択することで、地域医療を持続可能なものとすることに、地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
令和5年10月のお知らせ
放送日:令和5年10月15日
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、コロナウイルス感染状況と当院の基本理念と基本方針についてお話します。
まずは、コロナウイルスの感染状況についてですが、8月末から9月初旬をピークとしてその後減少しています。当院の状況をみると、9月の時間外患者の24.6%がコロナ感染の患者でしたが、10月になってからは7.7%に減っています。一方インフルエンザと診断された方の比率は、9月は2.7%でしたが、10月になって11.5%と急速に感染が拡大していることが伺えます。これから森町では祭りなどのイベントが開催されますので、感染には十分注意してください。
次に、当院の基本理念についてお話します。ホームページにも載せていますが、当院の基本理念は、「患者さまの人権を尊重し、心の通った医療を実践することで、地域と共に在る病院を目指します」とされています。地域と共に在る病院というのは、当院の役割である生活圏の医療を、あくまでも地域住民とともに作り上げていくものだという考えに基づいています。その点で、病院と地域の架け橋となる、「森町病院友の会」の活動は極めて重要であると考えています。先日も友の会主催による当院整形外科の後迫医師による講演には、非常に多くの方に参加していただきありがたく思います。これからも、当院は地域に情報を発信していきたいと思います。
また、患者さん毎の治療においても、情報を共有することは極めて重要だと考えています。理念に続く基本方針の2番目に、「よく聴き、よく説明し、十分な理解を得て医療を提供します」と書かれています。しかしながら、今でもたまに、患者さんやご家族は医師に対して何も言えないという言葉を聞くことがあります。専門家と一般の方には、持てる情報に格差があるのは確かです。これを医療情報の非対称性と言います。しかしながら医療とは、医療従事者と患者さんやご家族とがともに協力して病気に立ち向かう作業です。専門家には患者さんやご家族に正しい情報を伝える義務があり、患者さんやご家族は自ら選択する責務があります。専門家は患者さんにもわかるように選択肢を伝える努力が必要であり、患者さんやご家族には、伝えられた情報や選択肢を理解し決定することが求められます。決定するのは医師ではなく、あくまでも患者さんやご家族です。もしも伝えられた情報が理解できない、あるいは提示された治療方針に納得がいかない場合には、その旨を医師に伝えてください。医師が忙しそうで何も言えないという声も聴かれますが、直接医師に言えない場合でも、看護師や事務職、理学療法士や社会福祉士、あるいはケアマネージャーや地域包括支援センターの職員に相談してみるのもよいと思います。先月の同報無線でもお話しましたが、今やチーム森町と言える多職種の情報共有の仕組みができているのが森町の強みです。現在、当院1階のATMを取り除いた場所に、森町よろず相談室を設置しています。そのような窓口を利用するのも良いでしょう。いずれにせよ、これからの医療は、専門家にゆだねるのではなく、ともに作り上げていくものだという当院の理念をご理解いただき、地域の皆様のご協力を改めてお願いしたいと思います。
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、コロナウイルス感染状況と当院の基本理念と基本方針についてお話します。
まずは、コロナウイルスの感染状況についてですが、8月末から9月初旬をピークとしてその後減少しています。当院の状況をみると、9月の時間外患者の24.6%がコロナ感染の患者でしたが、10月になってからは7.7%に減っています。一方インフルエンザと診断された方の比率は、9月は2.7%でしたが、10月になって11.5%と急速に感染が拡大していることが伺えます。これから森町では祭りなどのイベントが開催されますので、感染には十分注意してください。
次に、当院の基本理念についてお話します。ホームページにも載せていますが、当院の基本理念は、「患者さまの人権を尊重し、心の通った医療を実践することで、地域と共に在る病院を目指します」とされています。地域と共に在る病院というのは、当院の役割である生活圏の医療を、あくまでも地域住民とともに作り上げていくものだという考えに基づいています。その点で、病院と地域の架け橋となる、「森町病院友の会」の活動は極めて重要であると考えています。先日も友の会主催による当院整形外科の後迫医師による講演には、非常に多くの方に参加していただきありがたく思います。これからも、当院は地域に情報を発信していきたいと思います。
また、患者さん毎の治療においても、情報を共有することは極めて重要だと考えています。理念に続く基本方針の2番目に、「よく聴き、よく説明し、十分な理解を得て医療を提供します」と書かれています。しかしながら、今でもたまに、患者さんやご家族は医師に対して何も言えないという言葉を聞くことがあります。専門家と一般の方には、持てる情報に格差があるのは確かです。これを医療情報の非対称性と言います。しかしながら医療とは、医療従事者と患者さんやご家族とがともに協力して病気に立ち向かう作業です。専門家には患者さんやご家族に正しい情報を伝える義務があり、患者さんやご家族は自ら選択する責務があります。専門家は患者さんにもわかるように選択肢を伝える努力が必要であり、患者さんやご家族には、伝えられた情報や選択肢を理解し決定することが求められます。決定するのは医師ではなく、あくまでも患者さんやご家族です。もしも伝えられた情報が理解できない、あるいは提示された治療方針に納得がいかない場合には、その旨を医師に伝えてください。医師が忙しそうで何も言えないという声も聴かれますが、直接医師に言えない場合でも、看護師や事務職、理学療法士や社会福祉士、あるいはケアマネージャーや地域包括支援センターの職員に相談してみるのもよいと思います。先月の同報無線でもお話しましたが、今やチーム森町と言える多職種の情報共有の仕組みができているのが森町の強みです。現在、当院1階のATMを取り除いた場所に、森町よろず相談室を設置しています。そのような窓口を利用するのも良いでしょう。いずれにせよ、これからの医療は、専門家にゆだねるのではなく、ともに作り上げていくものだという当院の理念をご理解いただき、地域の皆様のご協力を改めてお願いしたいと思います。
令和5年9月のお知らせ
放送日:令和5年9月15日
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、地域リハビリテーションと当院の取り組みについてお話します。
地域リハビリテーションとは、障害のある子供や成人・高齢者とその家族が、住み慣れたところで、一生安全に、その人らしくいきいきとした生活ができるよう、保険・医療・福祉・介護及び地域住民を含め生活に関わるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行う活動のすべてを言います。地域リハビリテーションを進めるための課題として、1.リハビリテーションサービスの整備と充実、2.連携活動の強化とネットワークの構築、3.リハビリテーションの啓発と地域づくりの推進などが挙げられます。まず1番目の、リハビリテーションサービスの整備と充実についてですが、当院は、急性期、回復期のリハビリテーションを入院で行っています。さらに生活の場に復帰した後の通所リハビリテーションも行っています。今年度から、リハビリテーション科専属の常勤医師を配置し、また浜松医大や磐田市立総合病院からリハビリ専門医の定期的な派遣もあり、充実したリハビリテーションの体制を整えています。2番目の、連携活動の強化とネットワークの構築ですが、医療・介護の専門職や行政・住民の代表も参加した多職種合同カンファレンスを行うなど顔の見える関係づくりに取り組み、今や「チーム森町」と言っていい強固なネットワークを構築しています。3番目のリハビリテーションの啓発と地域づくりの支援ですが、森町病院友の会の主催する地域懇談会などを通じて、地域に情報を発信することで、多くの住民が自ら健康づくりに取り組んでいます。このような取り組みが進んでいることは、森町の強みと言っていいでしょう。
今後の課題は、さらに予防的活動に力を入れることです。森町は、今後も後期高齢者の絶対数が増えてきます。加齢によっておこる問題点の一つとして、呑み込みの機能が低下し、誤嚥性肺炎を起こしやすくなることが挙げられます。ひとたび誤嚥性肺炎を起こすと、入院し急性期を脱した後、リハビリテーションをおこなって生活の場に復帰することになります。このようなことを何度か繰り返し、入院のたびに呑み込みの機能が段階的に低下し、最終的には命を落とす方もいます。高齢になればなるほど、ひとたび重症化してからはなかなか元の通りに回復することは難しくなります。そのため、これからはなるべく悪くならないうちに予防的介入を行うことが求められます。
当院では、嚥下造影検査など早期に嚥下機能の低下を発見するための検査体制を整えています。ご心配な方は、かかりつけ医やケアマネージャー、地域包括支援センターや町の福祉課に相談してみてください。何事も早期発見、早期治療です。引き続き地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、地域リハビリテーションと当院の取り組みについてお話します。
地域リハビリテーションとは、障害のある子供や成人・高齢者とその家族が、住み慣れたところで、一生安全に、その人らしくいきいきとした生活ができるよう、保険・医療・福祉・介護及び地域住民を含め生活に関わるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行う活動のすべてを言います。地域リハビリテーションを進めるための課題として、1.リハビリテーションサービスの整備と充実、2.連携活動の強化とネットワークの構築、3.リハビリテーションの啓発と地域づくりの推進などが挙げられます。まず1番目の、リハビリテーションサービスの整備と充実についてですが、当院は、急性期、回復期のリハビリテーションを入院で行っています。さらに生活の場に復帰した後の通所リハビリテーションも行っています。今年度から、リハビリテーション科専属の常勤医師を配置し、また浜松医大や磐田市立総合病院からリハビリ専門医の定期的な派遣もあり、充実したリハビリテーションの体制を整えています。2番目の、連携活動の強化とネットワークの構築ですが、医療・介護の専門職や行政・住民の代表も参加した多職種合同カンファレンスを行うなど顔の見える関係づくりに取り組み、今や「チーム森町」と言っていい強固なネットワークを構築しています。3番目のリハビリテーションの啓発と地域づくりの支援ですが、森町病院友の会の主催する地域懇談会などを通じて、地域に情報を発信することで、多くの住民が自ら健康づくりに取り組んでいます。このような取り組みが進んでいることは、森町の強みと言っていいでしょう。
今後の課題は、さらに予防的活動に力を入れることです。森町は、今後も後期高齢者の絶対数が増えてきます。加齢によっておこる問題点の一つとして、呑み込みの機能が低下し、誤嚥性肺炎を起こしやすくなることが挙げられます。ひとたび誤嚥性肺炎を起こすと、入院し急性期を脱した後、リハビリテーションをおこなって生活の場に復帰することになります。このようなことを何度か繰り返し、入院のたびに呑み込みの機能が段階的に低下し、最終的には命を落とす方もいます。高齢になればなるほど、ひとたび重症化してからはなかなか元の通りに回復することは難しくなります。そのため、これからはなるべく悪くならないうちに予防的介入を行うことが求められます。
当院では、嚥下造影検査など早期に嚥下機能の低下を発見するための検査体制を整えています。ご心配な方は、かかりつけ医やケアマネージャー、地域包括支援センターや町の福祉課に相談してみてください。何事も早期発見、早期治療です。引き続き地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
令和5年8月のお知らせ
放送日:令和5年8月15日
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、当院の専門外来についてお話します。
当院は、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、免疫内科、神経内科、心療内科の専門外来を設けています。いずれも非常勤医師によるもので、診療日の頻度は週に1回の科もあれば、2週に1回、あるいは月に1回の科もあります。基本的には院内紹介の患者さんを診ることになっています。したがって直接専門外来を受診したい方は受け付けていません。まずは、当院内科を受診していただき、医師の判断で専門外来での診療が必要とされれば院内紹介という形になります。このことは、時間的に限られた専門外来で、直接多くの初診の患者さんを受けつけると、十分な診療が不可能になるためです。専門性を活かすためにはかかりつけ医により専門的な診療が必要と判断された方に限定して診療を行う必要があります。また、専門的な診療が終了した後の継続的診療は、かかりつけ医がみることになります。当院の内科は、基本的に専門領域に関わらず内科の受診を希望するすべての患者さんを受け付けています。直接専門外来の受診を希望される方は、その領域を標榜している医療機関を受診してください。どの診療科を受診すればよいかわからない場合は、まずは家庭医療クリニックを受診してください。必要があれば専門外来につなげます。以上のことは、限られた医療資源を有効に機能させるために、医療機関の機能分化と連携が必要であるからです。当院と森町家庭医療クリニックは、かかりつけ医機能を重視しています。それは、多くの患者さんが必ずしも一つの専門性だけでは解決しない健康問題を抱えているためです。当院は、これまでも悪くなってから医療機関にかかるより、健康を維持するために医療と関わることを呼び掛けてきました。その点から、日頃からかかりつけ医を持つことをお勧めしています。
暑い日が連日続き、熱中症が疑われる患者さんの受診が続いています。熱中症対策には十分注意してください。また、コロナ患者さんも連日外来を受診し、森町でも確実に増加しています。人の集まる場所ではやはり感染のリスクが高くなります。ほとんどの方が軽症で済んでいますが、病棟の入院患者はリスクが高く、やはり病棟という治療を目的とした場では、クラスターの発生は極力避ける必要があります。そのため、患者さんとの面会では時間など一定の制限を設けており、また入院中の患者さんの外出、外泊は極力控えていただいています。5類に移行した後も、病棟という特殊な状況では、感染対策が重要であることをご理解いただきたいと思います。引き続き地域の皆様のご理解、ご協力をお願いします。
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、当院の専門外来についてお話します。
当院は、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、免疫内科、神経内科、心療内科の専門外来を設けています。いずれも非常勤医師によるもので、診療日の頻度は週に1回の科もあれば、2週に1回、あるいは月に1回の科もあります。基本的には院内紹介の患者さんを診ることになっています。したがって直接専門外来を受診したい方は受け付けていません。まずは、当院内科を受診していただき、医師の判断で専門外来での診療が必要とされれば院内紹介という形になります。このことは、時間的に限られた専門外来で、直接多くの初診の患者さんを受けつけると、十分な診療が不可能になるためです。専門性を活かすためにはかかりつけ医により専門的な診療が必要と判断された方に限定して診療を行う必要があります。また、専門的な診療が終了した後の継続的診療は、かかりつけ医がみることになります。当院の内科は、基本的に専門領域に関わらず内科の受診を希望するすべての患者さんを受け付けています。直接専門外来の受診を希望される方は、その領域を標榜している医療機関を受診してください。どの診療科を受診すればよいかわからない場合は、まずは家庭医療クリニックを受診してください。必要があれば専門外来につなげます。以上のことは、限られた医療資源を有効に機能させるために、医療機関の機能分化と連携が必要であるからです。当院と森町家庭医療クリニックは、かかりつけ医機能を重視しています。それは、多くの患者さんが必ずしも一つの専門性だけでは解決しない健康問題を抱えているためです。当院は、これまでも悪くなってから医療機関にかかるより、健康を維持するために医療と関わることを呼び掛けてきました。その点から、日頃からかかりつけ医を持つことをお勧めしています。
暑い日が連日続き、熱中症が疑われる患者さんの受診が続いています。熱中症対策には十分注意してください。また、コロナ患者さんも連日外来を受診し、森町でも確実に増加しています。人の集まる場所ではやはり感染のリスクが高くなります。ほとんどの方が軽症で済んでいますが、病棟の入院患者はリスクが高く、やはり病棟という治療を目的とした場では、クラスターの発生は極力避ける必要があります。そのため、患者さんとの面会では時間など一定の制限を設けており、また入院中の患者さんの外出、外泊は極力控えていただいています。5類に移行した後も、病棟という特殊な状況では、感染対策が重要であることをご理解いただきたいと思います。引き続き地域の皆様のご理解、ご協力をお願いします。
令和5年7月のお知らせ
放送日:令和5年7月15日
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、人生の最終段階における医療についてお話します。
近年は人生100年時代と言われ、多くの方が90歳以上の超高齢期を過ごす時代を迎えています。森町の本年4月30日時点での高齢化率は36.1%で、これは日本全体の高齢化率がピークとなる2040年の値にほぼ合致しています。森町はその点では日本の未来を先取りしているといってもよいかもしれません。森町の高齢者率の上昇は今後他の市町に比べて緩やかとなります。しかしながら、今よりもさらに高齢者の中でも超高齢者の割合が増加し、多くの方が人生の最終段階を迎えることになります。森町はもうすでに多くの方が死を迎える多死社会に入ったと言えるかもしれません。
そんな時代を迎え、医療界にとってテーマとなるのが、人々の価値観を人生の最期までいかに支え、またその最終段階においてそれぞれの希望に沿った医療やケアを提供することができるかということです。
そこで、わが国ではアドバンス・ケア・プランニング、略してACP、また日本語の表現としては人生会議と言われる考え方を進めようとしています。これは、ご本人がどのような人生を過ごしたいか、あるいは突発的なけがや病気でご自分の意思が表明できなくなったときに、どのような医療やケアを受けたいかなどを、前もってご家族や身近な人、医療や介護の専門家などと話をしておくこと、また場合によっては自分の意思を誰に代弁してもらいたいかを前もって決めておくことなどを勧める考え方です。このような取り組みによってできるだけご本人の意思に沿った対応をしていこうという試みです。アドバンスというのは先取りするという意味です。昔から元気なうちに自分の意思を文書化しておく事前指示書などの手段もありましたが、必ずしもうまく機能しませんでした。このことは、一度意思を表明したとしても人の思いは変わるものだということ、またご家族や医療者の思いと必ずしも合致しないことなどが社会に受け入れられない要因であったかもしれません。ACPという考え方は、関りを持つできるだけ多くの人と思いを共有すること、また人の思いは変わるのだという前提に立って、何度も繰り返すことが重要だという考え方です。会議という形式的な形ではなく雑談のような会話でもよいのです。大事なことは対話を繰り返すことであり、たとえ明らかな選択や決定を表明できなくても、対話によって得られた情報から、関りを持つ人たちがその人の思いを類推することが可能となります。ご家族とはなかなか話しづらい場合は、かかりつけ医や看護師、ケアマネージャー、相談員などと話をしておくことも大切です。最終的には、日頃から一緒に過ごしてきたご家族の思いと専門家チームが得ている情報を交えてご本人の意思決定を支援していこうというのがACPの考え方です。森町ではこれまでも、多職種連携を進め、在宅医療も実現可能な選択肢として提示してきました。その結果、令和4年度の当院と森町家庭医療クリニックの死亡診断書の統計では、自宅での看取り率が全死亡の47.0%と、全国統計の13.6%と比べて極めて高い数値となっています。このことは、できるだけご本人、ご家族の希望に沿った形での実現可能な選択肢の一つとして在宅医療の仕組みを構築してきた結果であると考えています。まずはご自分の思いを誰かに伝えてみてはいかがでしょう。そこから生まれる対話によって互いの理解が進むことがACPの第一歩だと思います。当院は、今後とも地域の皆様と協力し、新しい時代の医療に取り組んでまいりたいと考えています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、人生の最終段階における医療についてお話します。
近年は人生100年時代と言われ、多くの方が90歳以上の超高齢期を過ごす時代を迎えています。森町の本年4月30日時点での高齢化率は36.1%で、これは日本全体の高齢化率がピークとなる2040年の値にほぼ合致しています。森町はその点では日本の未来を先取りしているといってもよいかもしれません。森町の高齢者率の上昇は今後他の市町に比べて緩やかとなります。しかしながら、今よりもさらに高齢者の中でも超高齢者の割合が増加し、多くの方が人生の最終段階を迎えることになります。森町はもうすでに多くの方が死を迎える多死社会に入ったと言えるかもしれません。
そんな時代を迎え、医療界にとってテーマとなるのが、人々の価値観を人生の最期までいかに支え、またその最終段階においてそれぞれの希望に沿った医療やケアを提供することができるかということです。
そこで、わが国ではアドバンス・ケア・プランニング、略してACP、また日本語の表現としては人生会議と言われる考え方を進めようとしています。これは、ご本人がどのような人生を過ごしたいか、あるいは突発的なけがや病気でご自分の意思が表明できなくなったときに、どのような医療やケアを受けたいかなどを、前もってご家族や身近な人、医療や介護の専門家などと話をしておくこと、また場合によっては自分の意思を誰に代弁してもらいたいかを前もって決めておくことなどを勧める考え方です。このような取り組みによってできるだけご本人の意思に沿った対応をしていこうという試みです。アドバンスというのは先取りするという意味です。昔から元気なうちに自分の意思を文書化しておく事前指示書などの手段もありましたが、必ずしもうまく機能しませんでした。このことは、一度意思を表明したとしても人の思いは変わるものだということ、またご家族や医療者の思いと必ずしも合致しないことなどが社会に受け入れられない要因であったかもしれません。ACPという考え方は、関りを持つできるだけ多くの人と思いを共有すること、また人の思いは変わるのだという前提に立って、何度も繰り返すことが重要だという考え方です。会議という形式的な形ではなく雑談のような会話でもよいのです。大事なことは対話を繰り返すことであり、たとえ明らかな選択や決定を表明できなくても、対話によって得られた情報から、関りを持つ人たちがその人の思いを類推することが可能となります。ご家族とはなかなか話しづらい場合は、かかりつけ医や看護師、ケアマネージャー、相談員などと話をしておくことも大切です。最終的には、日頃から一緒に過ごしてきたご家族の思いと専門家チームが得ている情報を交えてご本人の意思決定を支援していこうというのがACPの考え方です。森町ではこれまでも、多職種連携を進め、在宅医療も実現可能な選択肢として提示してきました。その結果、令和4年度の当院と森町家庭医療クリニックの死亡診断書の統計では、自宅での看取り率が全死亡の47.0%と、全国統計の13.6%と比べて極めて高い数値となっています。このことは、できるだけご本人、ご家族の希望に沿った形での実現可能な選択肢の一つとして在宅医療の仕組みを構築してきた結果であると考えています。まずはご自分の思いを誰かに伝えてみてはいかがでしょう。そこから生まれる対話によって互いの理解が進むことがACPの第一歩だと思います。当院は、今後とも地域の皆様と協力し、新しい時代の医療に取り組んでまいりたいと考えています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
令和5年6月のお知らせ
放送日:令和5年6月15日
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は当院の入院患者さんへの面会についてお知らせします。
当院は、コロナ禍に突入してから現在まで、院内感染防止の観点から、入院患者様への面会を原則禁止としてきました。今年の5月8日付で新型コロナ感染症が感染症法上の5類となってから1か月以上が経過し、その後の爆発的な感染拡大がみられないことから、6月15日から面会禁止を原則解除することとしました。しかしながら、爆発的な感染拡大はみられないとはいえ、指定医療機関からの報告による定点観測では、徐々に感染者が増加しているのも事実です。6月13日時点で、県内医療機関のコロナ病床使用率は、東部で41.7%、中部で21.7%、西部で37.4%であり、県内全体で112人の入院患者が報告されています。西部地域は1週間前の45.1%から7.7%減少しましたが、東部は34.5%から7.2%の増加、中部は8.5%から13.2%の増加が認められます。中東遠地域の病床占有率は、この1週間で、14.3%から32.1%と増加しています。県内全体の入院患者のうち、重症者の割合は2.7%、中等症が33.9%、軽症者が63.4%と軽症の割合が比較的高いものの、わずかながら重症患者の報告もあります。このような事実を踏まえ、当院としては面会禁止を解除するものの、面会の仕方には一定の制限を設けたいと考えています。具体的には、面会時間は休日も含めて14時から18時の間とし、一回の面会は15分以内とさせていただきます。面会者は、患者様のご家族2名までとし、中学生以上の方に限らせていただきます。発熱や体調不良のある方は面会をご遠慮ください。また、面会時にはマスクの着用にご協力ください。
入院中の患者様は、病気の治療のためにやむを得ず生活の場そのものを一時的に病棟にうつしている状況です。そのような場ではできるだけ治療に専念し、可能な限り早く本来の生活の場に復帰することを目指しています。院内感染防止の観点からだけではなく、患者様が治療に専念できるように、不必要な面会はなるべく控えていただくことも大切です。一方、治療が目的とは言え、ご家族と離れて暮らすことは心細さもあり、そのことで気力が低下することになれば治療の妨げにもなり得ます。そのような観点から、ご家族との面会も治療の一環とも言えます。したがって、今後は感染対策とのバランスを取りながら面会も可能としていくことが重要と思われます。
当院は、治療を目的とした急性期病棟だけでなく、病状を安定させるための地域包括ケア病棟、機能を回復させるための回復期リハビリテーション病棟を運営しています。いずれの病棟も機能は異なるとはいえ、すべて本来の生活の場に復帰させることが目的です。当院は、このように患者様毎に適切な選択肢を提供することで、生活者を支える医療を目指しています。引き続き地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は当院の入院患者さんへの面会についてお知らせします。
当院は、コロナ禍に突入してから現在まで、院内感染防止の観点から、入院患者様への面会を原則禁止としてきました。今年の5月8日付で新型コロナ感染症が感染症法上の5類となってから1か月以上が経過し、その後の爆発的な感染拡大がみられないことから、6月15日から面会禁止を原則解除することとしました。しかしながら、爆発的な感染拡大はみられないとはいえ、指定医療機関からの報告による定点観測では、徐々に感染者が増加しているのも事実です。6月13日時点で、県内医療機関のコロナ病床使用率は、東部で41.7%、中部で21.7%、西部で37.4%であり、県内全体で112人の入院患者が報告されています。西部地域は1週間前の45.1%から7.7%減少しましたが、東部は34.5%から7.2%の増加、中部は8.5%から13.2%の増加が認められます。中東遠地域の病床占有率は、この1週間で、14.3%から32.1%と増加しています。県内全体の入院患者のうち、重症者の割合は2.7%、中等症が33.9%、軽症者が63.4%と軽症の割合が比較的高いものの、わずかながら重症患者の報告もあります。このような事実を踏まえ、当院としては面会禁止を解除するものの、面会の仕方には一定の制限を設けたいと考えています。具体的には、面会時間は休日も含めて14時から18時の間とし、一回の面会は15分以内とさせていただきます。面会者は、患者様のご家族2名までとし、中学生以上の方に限らせていただきます。発熱や体調不良のある方は面会をご遠慮ください。また、面会時にはマスクの着用にご協力ください。
入院中の患者様は、病気の治療のためにやむを得ず生活の場そのものを一時的に病棟にうつしている状況です。そのような場ではできるだけ治療に専念し、可能な限り早く本来の生活の場に復帰することを目指しています。院内感染防止の観点からだけではなく、患者様が治療に専念できるように、不必要な面会はなるべく控えていただくことも大切です。一方、治療が目的とは言え、ご家族と離れて暮らすことは心細さもあり、そのことで気力が低下することになれば治療の妨げにもなり得ます。そのような観点から、ご家族との面会も治療の一環とも言えます。したがって、今後は感染対策とのバランスを取りながら面会も可能としていくことが重要と思われます。
当院は、治療を目的とした急性期病棟だけでなく、病状を安定させるための地域包括ケア病棟、機能を回復させるための回復期リハビリテーション病棟を運営しています。いずれの病棟も機能は異なるとはいえ、すべて本来の生活の場に復帰させることが目的です。当院は、このように患者様毎に適切な選択肢を提供することで、生活者を支える医療を目指しています。引き続き地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
令和5年5月のお知らせ
放送日:令和5年5月15日
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、5類に移行した後のコロナウイルス対応についてお話します。
5月8日付で、それまで2類感染症相当だった新型コロナウイルス感染症も、インフルエンザと同等の5類感染症の扱いとなりました。そのことで、コロナウイルスに感染したとしても、法的な行動制限は無くなり、基本的にはその対応は各自の判断にまかされるということになります。しかしながら、コロナウイルス感染症が決してなくなったわけではなく、5月1日から7日までの1日当たり新規感染者数の平均は、全国で10460人、静岡県で163人です。5月10日時点での静岡県の病床占有率は8.2%、県西部で5.3%、中東遠圏域での入院患者数は1人です。当院では4月11日以後コロナ感染症による入院患者数は0が続いていますが、外来では散発的にコロナ陽性者が認められ、5月8日から10日の3日間で6名の陽性者が認められています。散発的とはいえ、常にコロナ患者が発生している中で、社会活動が再開したことから、誰もがいつどこでコロナに感染してもおかしくありません。国はもしも感染した場合、5日間は人との接触を避け、10日間はマスクを着用するなどを勧めています。季節性インフルエンザと違い、コロナウイルス感染症は、季節に関係なく1年中発生がみられることから、今後も各個人で感染を防ぐよう注意してください。マスクの着用は感染対策として有効であることは確証が得られています。特に自分が感染した場合に、人にうつさないようにする効果が期待されます。現在ワクチン接種がいきわたったことなどから、感染しても症状が軽いか、まったく無症状の場合もあります。その場合でも人にうつす可能性があることに注意してください。基礎疾患のある高齢者と接触するときなどは、自分がウイルスに感染していることを想定して、マスクを着用することをお勧めします。
現在、日本のコロナウイルスの大多数が、新しい変異株のXBB1.5に置き換わっています。これは、オミクロン株のBA2から変異したもので、海外で拡大したものが国内でも広がったものと思われます。したがって、これまで感染したことのある方も、再度感染する可能性があることに注意してください。このタイプは、ほかのオミクロン株よりも感染力が強い可能性が指摘されていますが、重症化率は変わらないようです。また、ワクチン接種の効果も一定程度認められます。森町でも、5月13日から7月1日までの間、高齢者や基礎疾患のある方を対象としてワクチンの集団接種を行います。また、秋から冬にかけて一般の方のワクチン接種も予定されています。今後も新たな感染拡大を防ぐため、可能であれば接種しておいた方が良いと思われます。
コロナウイルスに限らず、様々な感染症は、マスクの着用などの適切な対応で防ぐことができます。コロナ禍で学んだことを、今後の健康管理にぜひとも活かしていただきたいと思います。地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、5類に移行した後のコロナウイルス対応についてお話します。
5月8日付で、それまで2類感染症相当だった新型コロナウイルス感染症も、インフルエンザと同等の5類感染症の扱いとなりました。そのことで、コロナウイルスに感染したとしても、法的な行動制限は無くなり、基本的にはその対応は各自の判断にまかされるということになります。しかしながら、コロナウイルス感染症が決してなくなったわけではなく、5月1日から7日までの1日当たり新規感染者数の平均は、全国で10460人、静岡県で163人です。5月10日時点での静岡県の病床占有率は8.2%、県西部で5.3%、中東遠圏域での入院患者数は1人です。当院では4月11日以後コロナ感染症による入院患者数は0が続いていますが、外来では散発的にコロナ陽性者が認められ、5月8日から10日の3日間で6名の陽性者が認められています。散発的とはいえ、常にコロナ患者が発生している中で、社会活動が再開したことから、誰もがいつどこでコロナに感染してもおかしくありません。国はもしも感染した場合、5日間は人との接触を避け、10日間はマスクを着用するなどを勧めています。季節性インフルエンザと違い、コロナウイルス感染症は、季節に関係なく1年中発生がみられることから、今後も各個人で感染を防ぐよう注意してください。マスクの着用は感染対策として有効であることは確証が得られています。特に自分が感染した場合に、人にうつさないようにする効果が期待されます。現在ワクチン接種がいきわたったことなどから、感染しても症状が軽いか、まったく無症状の場合もあります。その場合でも人にうつす可能性があることに注意してください。基礎疾患のある高齢者と接触するときなどは、自分がウイルスに感染していることを想定して、マスクを着用することをお勧めします。
現在、日本のコロナウイルスの大多数が、新しい変異株のXBB1.5に置き換わっています。これは、オミクロン株のBA2から変異したもので、海外で拡大したものが国内でも広がったものと思われます。したがって、これまで感染したことのある方も、再度感染する可能性があることに注意してください。このタイプは、ほかのオミクロン株よりも感染力が強い可能性が指摘されていますが、重症化率は変わらないようです。また、ワクチン接種の効果も一定程度認められます。森町でも、5月13日から7月1日までの間、高齢者や基礎疾患のある方を対象としてワクチンの集団接種を行います。また、秋から冬にかけて一般の方のワクチン接種も予定されています。今後も新たな感染拡大を防ぐため、可能であれば接種しておいた方が良いと思われます。
コロナウイルスに限らず、様々な感染症は、マスクの着用などの適切な対応で防ぐことができます。コロナ禍で学んだことを、今後の健康管理にぜひとも活かしていただきたいと思います。地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
令和5年4月のお知らせ
放送日:令和5年4月15日
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、当院の新たな診療体制と新型コロナが5類に移行した後の対応についてお話します。
まずは、本年度の当院の診療体制ですが、先月の同報無線でもお話した通り、4月1日付で整形外科医師2名が新たに赴任し、ほとんどの整形外科疾患への対応が可能となりました。これまで手術などは、他院に紹介せざるを得ない状況がありましたが、今年度からは当院での手術対応も可能となりました。関節の痛みなど、生活に不自由を感じながらも、遠くの病院にはかかりたくないなどの理由で受診を控えていた方は、ぜひ一度当院の整形外科に受診してください。その他の診療科の体制は、これまで通りです。家庭医療クリニックについては、医師の移動などで常勤医の数は昨年度よりも減っています。
これまで爆発的なコロナ患者数の増加のため、ある程度受診制限せざるを得ない状況がありましたが、今のようなコロナの新規感染者数が少ない状況が続く中では、できるだけ受診を希望される方は受け入れていく方針です。しかしながら、森町家庭医療クリニックは、研修施設でもあり、医学生や初期研修医の実習なども受け入れています。質の高い研修を行うために、ある程度患者数を調整しなければならないこともあることはご理解ください。そのような場合は、森町病院がバックアップします。家庭医療クリニックの診察予約が取れない場合は、当院にも受診の問い合わせをしてみてください。森町家庭医療クリニックと当院は一体的な運営で地域の皆様の必要に応えていきたいと思います。
新型コロナ感染症の新規感染者数は、全国的にも静岡県内でも下げ止まりからやや増加の傾向にあります。直近1週間の静岡県の1日当たり新規感染者数の平均は約160人です。この数は、県内で病床ひっ迫が問題となった第3波のピークよりもはるかに高い数値です。したがって、決してコロナ禍が終息したわけではありません。しかしながら、オミクロン株に変化してから重症化率は低く、ほとんどの感染者は自宅での療養が可能であることから、現在社会生活を制限しない方向に変わっています。5月8日からは、これまでの2類相当から5類扱いとなり、強制的に行動制限が行われることは無くなります。したがって今後はコロナ感染への対応は、それぞれの判断に任されることになります。しかしながら法的な対応が変わったとしても、感染症そのものが変わるわけではありません。今後も新規感染者数が一定程度発生し続けることが予想され、高齢者などは感染をきっかけとして入院を余儀なくされる場合もあり、引き続き感染には注意する必要があります。とは言え、通常の生活を取り戻すことも大切です。コロナ禍の結果、人々の感染症への認識は高まりました。またマスクなどの対策によって、コロナ感染ばかりでなく、インフルエンザ等他の感染症の発生も低く抑えられました。コロナ禍を経験して一人一人が学んだことを、今後の生活にどのように活かしていくかが大切です。病院は引き続き院内感染を防ぐ必要があります。
そのため、当面の間はある程度の面会制限も必要になります。そのことで、むしろ入院患者さんが治療に専念できるようにもなります。病院の面会の在り方などについては、今後も地域の皆様の声を聴きながら対応を考えていきたいと思います。引き続きご理解とご協力をお願いします。
担当者:院長 中村昌樹
おはようございます。森町病院院長の中村です。本日は、当院の新たな診療体制と新型コロナが5類に移行した後の対応についてお話します。
まずは、本年度の当院の診療体制ですが、先月の同報無線でもお話した通り、4月1日付で整形外科医師2名が新たに赴任し、ほとんどの整形外科疾患への対応が可能となりました。これまで手術などは、他院に紹介せざるを得ない状況がありましたが、今年度からは当院での手術対応も可能となりました。関節の痛みなど、生活に不自由を感じながらも、遠くの病院にはかかりたくないなどの理由で受診を控えていた方は、ぜひ一度当院の整形外科に受診してください。その他の診療科の体制は、これまで通りです。家庭医療クリニックについては、医師の移動などで常勤医の数は昨年度よりも減っています。
これまで爆発的なコロナ患者数の増加のため、ある程度受診制限せざるを得ない状況がありましたが、今のようなコロナの新規感染者数が少ない状況が続く中では、できるだけ受診を希望される方は受け入れていく方針です。しかしながら、森町家庭医療クリニックは、研修施設でもあり、医学生や初期研修医の実習なども受け入れています。質の高い研修を行うために、ある程度患者数を調整しなければならないこともあることはご理解ください。そのような場合は、森町病院がバックアップします。家庭医療クリニックの診察予約が取れない場合は、当院にも受診の問い合わせをしてみてください。森町家庭医療クリニックと当院は一体的な運営で地域の皆様の必要に応えていきたいと思います。
新型コロナ感染症の新規感染者数は、全国的にも静岡県内でも下げ止まりからやや増加の傾向にあります。直近1週間の静岡県の1日当たり新規感染者数の平均は約160人です。この数は、県内で病床ひっ迫が問題となった第3波のピークよりもはるかに高い数値です。したがって、決してコロナ禍が終息したわけではありません。しかしながら、オミクロン株に変化してから重症化率は低く、ほとんどの感染者は自宅での療養が可能であることから、現在社会生活を制限しない方向に変わっています。5月8日からは、これまでの2類相当から5類扱いとなり、強制的に行動制限が行われることは無くなります。したがって今後はコロナ感染への対応は、それぞれの判断に任されることになります。しかしながら法的な対応が変わったとしても、感染症そのものが変わるわけではありません。今後も新規感染者数が一定程度発生し続けることが予想され、高齢者などは感染をきっかけとして入院を余儀なくされる場合もあり、引き続き感染には注意する必要があります。とは言え、通常の生活を取り戻すことも大切です。コロナ禍の結果、人々の感染症への認識は高まりました。またマスクなどの対策によって、コロナ感染ばかりでなく、インフルエンザ等他の感染症の発生も低く抑えられました。コロナ禍を経験して一人一人が学んだことを、今後の生活にどのように活かしていくかが大切です。病院は引き続き院内感染を防ぐ必要があります。
そのため、当面の間はある程度の面会制限も必要になります。そのことで、むしろ入院患者さんが治療に専念できるようにもなります。病院の面会の在り方などについては、今後も地域の皆様の声を聴きながら対応を考えていきたいと思います。引き続きご理解とご協力をお願いします。