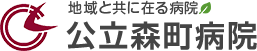医療安全管理室
当院における医療に係わる安全管理のための指針
事故のない安全な医療を提供していくためには、従事者一人一人が危機意識を持って、日々、患者さんへの医療提供にあたると同時に、医療に係わる知識や技術を一定のレベル以上に保つことが不可欠です。医療においては「人間はエラーを起こす」という前提に基づき、エラーを誘発しない環境や起こったエラーを吸収して事故を未然に防ぐ体制を構築していきます。
医療に係わる安全管理の体制
医療安全管理委員会
安全管理の体制の確保及び推進のための安全対策に関する重要事項等について審議し、方針を決定しています。
合計27名の委員 月1回開催
合計27名の委員 月1回開催
セーフティ-マネージャー会
定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保のために必要な業務改善などの具体的な対策を推進する。
医療安全に係わる体制を確保するための職員研修(年2回)を企画・運営。
医療安全対策に係る取り組みの評価のカンファレンスの開催 毎月第三月曜日
医療安全に係わる体制を確保するための職員研修(年2回)を企画・運営。
医療安全対策に係る取り組みの評価のカンファレンスの開催 毎月第三月曜日
医療安全カンファレンス
医療安全管理委員会との連携状況、院内研修の実績、看護師特定行為業務管理、患者などの相談件数及び相談内容、相談後の取り扱い、その他の医療安全管理者の活動実績を記録する。
医療安全対策に係る取り組み評価のためのカンファレンス 週1回程度開催
医療安全対策に係る取り組み評価のためのカンファレンス 週1回程度開催
医療に係わる安全管理のための従事者に対する研修に関する基本方針
- 個々の従事者の安全管理に対する意識の啓発、安全に業務を遂行するための技能、チーム医療の一員として意識の向上を図るため、病院全体に共通する安全管理に関する内容についての研修を年2回以上定期的に開催
- 新規採用職員及び新規に業務を行う者に対して当院の安全管理に対する基本的な考え方、方針、事項を周知させるとともに、その遵守を徹底
患者からの相談(意見・要望・苦情) への対応に関する体制
- 医療行為等に関する患者等からの相談(意見・要望・苦情)に対しては、 担当者及びその責任者などを決め、誠実に対応。患者さん・家族が不利益を受けないよう適切な配慮を行い、医療安全や医療事故などの相談については、医療安全管理者が対応しています。
- これら相談など意見・要望・苦情は、業務改善や安全対策の見直しに活用しています。